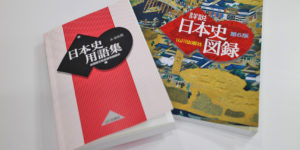進路探究塾 Mirai は小1生から高3生までを対象とした集団指導と,私立中高一貫校に通う生徒を対象とした個別指導を行なう進学塾で,2015年 3月に開塾したばかりの新しい塾です。
開塾から 3ヶ月半が経過しましたが,この間多くの方に当塾をお選びいただき,日を追うごとに賑やかさを増してきております。本当にありがとうございます。
当塾の指導を端的に言い表すと,“ひとつの場所で完結できる大学合格までの一貫指導” と “将来を見据えた指導” です。
中学生を例にとると,定期テスト得点向上や高校合格だけにとどまらない大学合格までの一貫指導を,映像授業に頼ることなく “集団指導+個別指導” で実現したのが私たちの指導です。
当塾は長い目で見た指導を行なう塾ですから,生徒や保護者様が「とにかく定期テストの得点を上げたい」というお考えをお持ちの場合,当塾はまったく合わないでしょう。
一口に塾と言っても,集団指導と個別指導,進学塾と補習塾,企業体と個人経営などさまざまな形態があります。
私は大手進学塾 (高校受験をメインとした中学生指導が中心の企業体) で18年の指導経験があり,複数校舎の統括も長年任されておりました。
夏を直前に控えたこの時期に塾を検討されるご家庭も多いでしょうから,私の過去の経験も踏まえて今回は “中学生・高校生の塾の選び方” に関して綴りたいと考えております。
ちなみに,私には中2生 (公立中) の娘と小5生 (もちろん公立小) の息子がおります。
塾教員としてのキャリアは18年を超えましたが,親となり初めて気が付けたことがたくさんあり,わが子を持つまで “わかったつもり” に過ぎなかったことがいかに多かったかを思い知らされました。
ですから,今回は “保護者としての観点” も交えながら綴らせていただきます。
まず,指導形態に関してです。
集団指導でも 6名から10名くらいの規模であったり20名を超えていたり,個別指導でも 1 : 1 のものから 3 : 1,さらには個別指導と呼べる代物ではないと考えますが 6 : 1 なんてのもあります。
お子さまにとって集団指導と個別指導のどちらがフィットする指導形態なのかを判断する必要があることと,集団指導・個別指導でもその種類はいろいろあるということを覚えておく必要があります。
いずれにしても,体験受講を経たうえでご検討されることをお勧めします。
さらには進学塾か補習塾かで方向性は異なります。
受験合格を目標とした進学塾,定期テスト対策指導や内申確保指導が中心の補習塾兼進学塾,学校の進度の後追いを基軸とした補習塾。
中学生向けの塾はまさに玉石混淆の状態で,きっちり区分することはかなり難しいように感じます。
何を目標に据えるのかで塾選びも変わってきます。
お子さまにとって何が最も必要なのか。それは定期テストなのか,高校受験なのか,あるいはその先なのかによって慎重に吟味しなければ,中学校卒業時に後悔の念が残ることになりかねません。
中学生向けの塾で言えば,「〇〇中 (公立) の定期テストで120点アップ!」などと謳い文句を見かけますが,保護者としての観点を入れれば前後の結果もきっちり提示してもらいたいところです。
合計点が230点だったものが350点になったのと350点が470点になったのとでは同じ「120点アップ」でも中身が全く異なりますからね。
どの生徒も一律に120点上げるなどということは不可能だと思いますし,さらにはどうやってそれだけの得点を上げたかの方法も重要視すべきです。
それが予想問題や過去問の雁字搦めで獲得したものであれば,生徒自身にテスト後よほどの意識改革がなければ,その生徒はずっとそれに縋って学習しなければならなくなります。
高校生向けの塾で言えば,定期テスト対策指導もします,一般入試での大学受験指導もしますというのは,卒業時に「二兎を追うものは一兎をも得ず」の結果になってしまうおそれがあります。
あくまで私見に過ぎませんが,先日のブログでも取り上げたように中学生と高校生は学習スタイルそのものが異なりますから,どちらかに振った形態のほうが望ましいと考えます。
いくら高校の定期テストで得点を重ねたところで志望する大学に合格できる保証はありませんし,高校は中学校の延長線上のようで延長線上ではないのです。
私立大に各種推薦入試での合格を目指すなら話は別です。このケースの場合は,個別指導塾や家庭教師などで定期テスト対策と内申確保に特化した指導を受けるべきでしょう。
当塾を『推薦する声』に寄稿してくれた河合くんと櫻井くんを指導していた頃も,私を含めた彼らの授業担当者は定期テスト対策指導を一切行ないませんでした。
上位高に通う意識の高い生徒なら,定期テストの学習程度であれば科目を問わず自分で熟せます。というより,難関大を目指すならできないとだめです。
高校の定期テストに関しては,あくまでも私たちは彼らが自習に来た際や授業後などに質問を受けるだけに過ぎませんでしたが,学年順位は 1桁や20位以内には常に入っていたようです。
高校の場合は入学の段階で学力レベルの選別がある程度完了しております。
上位高ならほぼ全ての生徒が一般入試で大学合格を目指し,各種推薦入試を経て大学に入学する生徒は少数派です (一部の高校では受験の雰囲気を乱さないために箝口令を敷くのだとか)。
逆に中位高で大学合格を目指す場合は各種推薦入試を経て大学に入学するケースがほとんどです。
最近は国公立大でも推薦入試を実施するところが増えつつありますが,割り当てられた定員がそれほど多くありませんからこれを第一志望に設定することは非常に危険です。
広く門戸の開かれた (定員が多く設定された) 一般入試での大学合格を目指すほうが無難だと言えます。
中学生・高校生を問わず,塾を選ぶ際は明確な方向性がきっちりと示され,その方向性がご家庭やお子さまのそれと合致できるところを選ばなければなりません。
最後に企業体か個人経営かに関してです。
複数校舎を展開する企業体の場合,全ての校舎で各種クオリティが均一であることはまずあり得ません。均一なのはテキストくらいです (これも校舎責任者の色が入ることもあり断言できません)。
私は以前に勤めていた塾で複数校舎の統括をしておりましたからよくわかります。自身の統括する各校舎の足並みとクオリティを揃えるのに腐心し続けていました。
よって,企業体にせよ個人経営にせよ,最終的に塾は “人” なのです。
その塾の塾長,企業体であればその校舎の責任者や授業を担当する教員とフィーリングが合うか。お子さまはもちろん保護者の方も含め,ここは慎重に見定めることが必要です。
どれほど崇高な目標を掲げていても,どれほど高い指導実績や合格実績が踊っていても,塾とお子さまが合わなければ望むものは得られないのです。
最後に,どのような形態の塾であっても,お子様も保護者様も納得したうえで選びたいのであれば,実際の指導中の様子や生徒がいる時間帯の塾内の様子を目にするのが一番です。
お子様は体験受講,保護者様はその体験授業の様子,または別日で見学させてもらうと,チラシはもちろん,ネットや伝聞では知り得ない内部の状況や真相を窺い知ることができます。
これを「生徒の気が散るから」などの理由で拒む塾は,見られると困る何らかの理由を抱えているのかもしれません。
その塾に通わせ始めることで何かを変えさせたい,現状を打開させたい,わが子にこんなふうになってほしい等,様々な想いや願いを込めて保護者様は塾へお子さまを預けることと思います。
上記したように,塾選びはつまるところ “人” です。一つ参考まで。