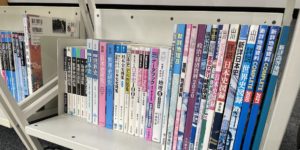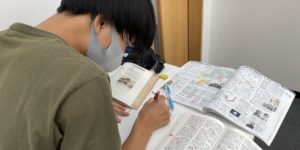今回のブログは,高校受験に関して私が思うところを綴ります。
まず,当塾は大学受験指導を主軸に据えてはいるものの,決して高校受験を軽視しているわけではないということを誤解のないように申し上げておきます。
公立中で学ぶ中学生は高校受験を経て成長することは揺るぎない事実ですし,高校受験は将来に向けた通過点として不可欠なものであることは間違いありません。

今春も岐阜学区の上位 3高 (岐阜高・岐阜北高・加納高 (普通科)) は多くの志願者を集めていましたね。
県内の公立高全体で見ると競争倍率は1.00倍ではありますが,岐阜学区内の上位 3高の競争倍率はそれぞれ1.18倍,1.29倍,1.26倍と,直近 5年間で見ても最も熾烈な争いになりました。
3高で計1,000名の入学枠に1,240名が挑む構図であり,これだけでも単純に競争倍率は1.24倍,およそ 5名に 1名が不合格になる計算です (県内の各高校の競争倍率はこちら)。
しかし,私は今春の上位 3高の競争倍率 (平均して1.24倍) は高いとは思っておらず,寧ろもう少し高くてもよいのではないかと考えています。
実際のところ,東大や京大,名大の合格者数ランキングに出てくるような他府県の上位公立高はもっと競争倍率が高いですし,大学受験で 1倍台の競争倍率になることは考えにくいからです。
難関大ともなると競争倍率は 3倍から 4倍に達することが一般的であるうえ,先日のブログでも申し上げたように,極端なケースでは10倍を超えるところもあります。

余談ではあるものの,私は塾で指導するようになって25年が経ちますが,公立高を受験した全員が合格を勝ち取った年はわずか 3度しかありません。
内申に不安を抱えていた,あるいは現場で力を発揮しきれなかった,またはわずかな可能性にかけて受験した等,不合格にはいろいろな要因があります。
倍率がそれほど高くないとは言っても「全員合格」というのは本当に難しいのです。
今春,当塾からは14名の中3生が公立高を受験し,岐阜北高と加納高でそれぞれ 1名ずつ,計 2名が不合格となりました。
彼らはいずれも岐阜東高へ進学することになりましたが,中学部の時点で志望校 (大学) が定まっていたこともあり,大学受験に向けて既に当塾の高校部で始動しています。

下記は県内の私立高に在籍して高校卒業までの間を当塾の高校部で学び,国立大の現役合格を勝ち取った卒塾生たちです。
[2016年 春] 1期生
岐阜東高 → 岐阜大学 教育学部
[2017年 春] 2期生
岐阜東高 → 名古屋大学 文学部
[2019年 春] 4期生
岐阜東高 → 岐阜大学 地域科学部
[2020年 春] 5期生
鶯谷高 → 名古屋大学 教育学部
岐阜東高 → 名古屋大学 工学部 (物理工学科)
岐阜東高 → 岐阜大学 教育学部
[2022年 春] 7期生
岐阜東高 → 奈良女子大学 生活環境学部 (食物栄養学科) [併願合格校 明治大・立命館大]
岐阜東高 → 岐阜大学 応用生物科学部 (生産環境科学科) [併願合格校 法政大・名城大]
彼らは公立高入試で岐阜高・岐阜北高・加納高への入学が叶わず,中学を卒業してからは県内の私立高へ進むことになりました。
しかし,大学入試は納得のいく形で終わらせたいという気概を持って高校卒業まで当塾で学び,それぞれ上記の大学の現役合格を勝ち取りました。
彼らが不合格となった公立高へ進学した生徒たち全員が,大学入試においても順風だったかと言えばそんなことはありません。
公立の上位高に合格したからといって胡坐をかいていると,いつの間にか “中学卒業時の序列” が崩れ,取り返しのつかない事態に陥っていることが往々にしてあります。
当塾のチラシにも謳っている通り,高校合格はゴールではなく通過点であるという意識を持つことが重要です。