
岐阜学区や西濃学区で通学圏内にある国公立大の医学部医学科といえば,県内の岐阜大と,愛知県の名古屋大・名古屋市立大の 3校が現実的なところだと思われます。
当ブログをお読みいただいている方々は,2022年春のこれら 3校の医学部医学科における岐阜県の高校出身者の数をご存じでしょうか。
以前のブログで目ぼしいところのみ概況を出したことがありますが,それぞれ岐阜県の高校出身者の数を申し上げると,岐阜大が36名,名古屋大が10名,名古屋市立大が 1名となっています。
もちろん,この数には過年度生 (浪人生) も含まれていますから,現役でこれら 3校の医学部医学科,中でも一般枠で合格を勝ち取るのは非常に難しいということは言うまでもありません。

岐大の36名の高校別内訳は,岐阜高が11名,大垣北高が 7名,美濃加茂高が 4名,恵那高・岐阜北高・斐太高・鶯谷高・高山西高が 2名,関高・多治見北高・岐阜東高・済美高が 1名です。
岐大は地元であることに加え,以前のブログでも申し上げたように定員の多くが地域枠に割り当てられていることからも,ご覧の通り岐阜県内の幅広い高校から合格者がいることがわかります。
定員110名に対して36名ということは占有率は32.7%ですから,岐阜大の医学部医学科はおよそ 3名に 1名が岐阜県の高校出身者ということになります。
続く名大の10名の高校別内訳は,岐阜高が 7名,関高・鶯谷高・高山西高が 1名で,隣県ではあるものの,旧帝大の一角で全国区ということから占有率は 9.3% (定員107名) に留まっています。
ただ,一昨年は岐阜高と多治見北高からそれぞれ 1名ずつの計 2名 (占有率 1.9%) でしたから,一昨年に比べると大躍進と言えます。

名市大の 1名は岐阜高の 1名のみで,調べてみると現役生ではなく過年度生 (浪人生) による合格であり,岐阜県の高校出身者による占有率はわずか 1.0% (定員97名) に過ぎない状況です。
高校別で見ると東海高・滝高・南山高の中高一貫 3高で占有率が30%を超え,旭丘高や岡崎高といった愛知県の公立高に加え,灘高やラ・サール高,西大和学園高といった全国区の名前もあります。
岐大の医学部医学科には東海地区以外の名だたる私立高の名前が多くは見当たらないことからも,名市大と岐大との間にはいろいろな意味で差があるのだと思います。
つまり,名市大の医学部医学科は岐阜県から距離的には近いところにあるものの,難易度的には手が届きそうで届かないところにあるということです。
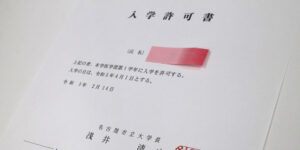
ちなみに,一昨年前の名市大の医学部医学科における岐阜県の高校出身者の数はというと,驚くべきことに 0名でした。
こうなった理由を当塾なりに分析し,医学部医学科を受験する塾生たち (岐高生) に話したところ「なるほどぉ…」と唸っていました。
先日のブログでもお伝えしたように,当塾の 8期生が名市大の医学部医学科に現役合格を勝ち取りましたから,今回のブログを作成しながら改めて彼の頑張りとその凄さを実感した次第です。






















